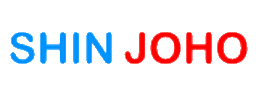1955年、当時の松下電器産業(ブランド名はNational)から電気カミソリ第1号が発売され、1981年には充電式(8時間充電で40分使用)で水洗い可能なお風呂シェーバーへと進化しました。その後、2002年に現在と同じ『ラムダッシュ』シリーズが登場し、2008年に社名がパナソニックになり、ブランド名もPanasonicへと変わりました。

パナソニックシェーバーの進化と歴史
今ではそのラインナップも多様化し、3枚刃~6枚刃、手のひらサイズにいたるまで、迷ってしまうほどの充実ぶりです。

比較表 | メンズシェーバー | Panasonic
充電方法として、以前はACアダプター+充電スタンドの製品が一般的でしたが、最近の製品にはUSB充電も採用されるようになっています。
そのUSB充電用のUSB(Type-C)ケーブルと本体のUSBソケットの接続部分が濡れた状態で充電するとショートが発生、発熱してソケット近辺が溶融・焦げに至る可能性があるため、対策を行ったUSBケーブルへと交換することになりました。
交換対象は、以下のとおり。
2023年7月1日~2024年5月9日に製造されたラムダッシュパームイン、計184,805台

ラムダッシュ パームイン ES-PV6A | メンズシェーバー | Panasonic

ラムダッシュ パームイン ES-PV3A | メンズシェーバー | Panasonic
2023年3月1日~2024年7月31日に製造されたエントリーシェーバー3枚刃、計189,164台
エントリーシェーバー 3枚刃 ES-RT4AU | メンズシェーバー | Panasonic

エントリーシェーバー 3枚刃 ES-RT1AU | メンズシェーバー | Panasonic
リコール メンズシェーバーに同梱のUSBケーブル交換のお知らせとお願い | Panasonic
消費者庁 経済産業省
送られてくる対策済のケーブルには、『加熱保護機能付き』『水付着時充電禁止』と書かれた大きなタグが付けられ、プラグに温度計のマークが押されています。


やけどに至る事故も複数発生しているため、大きく報道されています。
事故は2024年1月18日に初めて発生し、火災と認定された事故が27件、火災と認定されなかった事故が21件発生。そのうち、今年に入ってから家財に焦げが発生したものが1件、ケーブルを抜く際のやけどが3件発生したことにより、今回のリコールに至ったようです。
メンズシェーバー 事故防止に向けた同梱 USB ケーブル交換のリコール実施
最初の事故から1年4ヶ月後のリコールであることと、ウォッシャブルなシェーバーならではの充電時の危険性を予見した対策が必要であったことなど、AI(Geminiです)も渋めの評価をしています。
■Geminiの評価:
事故の件数と内容の重大性
発生件数: 対象製品(約37万台)に対して48件の事故が発生したことになります。この発生率をどう捉えるかは一概には言えませんが、消費者にとっては無視できない数であると考えられます。
人的被害の発生: 物損だけでなく、やけどという人的被害が3件報告されている点は非常に重く受け止めるべきです。製品の安全性において、人的被害の防止は最優先事項の一つです。
潜在的リスク: 報告された事故は氷山の一角である可能性も考慮する必要があります。同様の条件下で使用されたものの事故に至らなかったケースや、軽微な発熱でユーザーが気づかなかったり、メーカーに報告しなかったりしたケースも存在したかもしれません。
メーカーの対応時期と適切性
認知からリコールまでの期間: 最初の事故報告(2024年1月)からリコール発表(2025年5月)まで約1年4ヶ月が経過しています。この期間について、原因究明、製品テスト、対策(新しいケーブルの開発・準備)、関係省庁への報告・調整などに必要な時間であったとメーカー側は判断したのかもしれません。一方で、消費者保護の観点からは、特に人的被害が発生している状況下で、より迅速な注意喚起や対策の実施が望ましかったのではないか、という評価も成り立ちます。
リコールの内容: USBケーブルを過熱保護機能付きのものに無償交換するという対策自体は、特定された原因(水濡れ時のショートによる発熱)に対して直接的であり、再発防止策として合理的と考えられます。
情報公開: リコール発表時に事故件数や原因、対策を公表したことは、透明性の観点からは評価できます。しかし、それ以前の期間における消費者への情報提供や注意喚起の状況も、対応の適切性を評価する上で考慮される点です。
製品設計と安全性への配慮
予見可能性とリスク評価: シェーバーは洗面所など水回りで使用されることが多く、USB充電ポートが水に濡れるリスクは一定程度予見可能であったと考えられます。製品設計段階でのリスクアセスメントや、水濡れを想定した保護機能(例えば、ポートの防水性向上や、初期のケーブルにおけるより高度な安全装置など)が十分だったかという点は検証されるべきかもしれません。
ユーザビリティと安全性のバランス: USB Type-Cという汎用的な充電方式を採用することは利便性が高い一方で、その安全な使用方法(特に水濡れに対する注意)の周知や、構造的な安全対策が一層求められます。
企業倫理と社会的責任
企業には、安全な製品を提供するという基本的な社会的責任があります。事故情報を把握した後の社内での調査、原因究明、そしてリコールという経営判断に至るプロセスにおいて、消費者の安全を最優先する姿勢が一貫して取られていたかが問われます。これは外部からは見えにくい部分ですが、企業の信頼性に関わる重要な要素です。